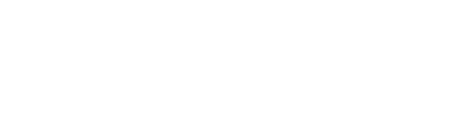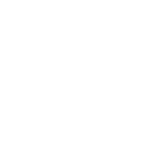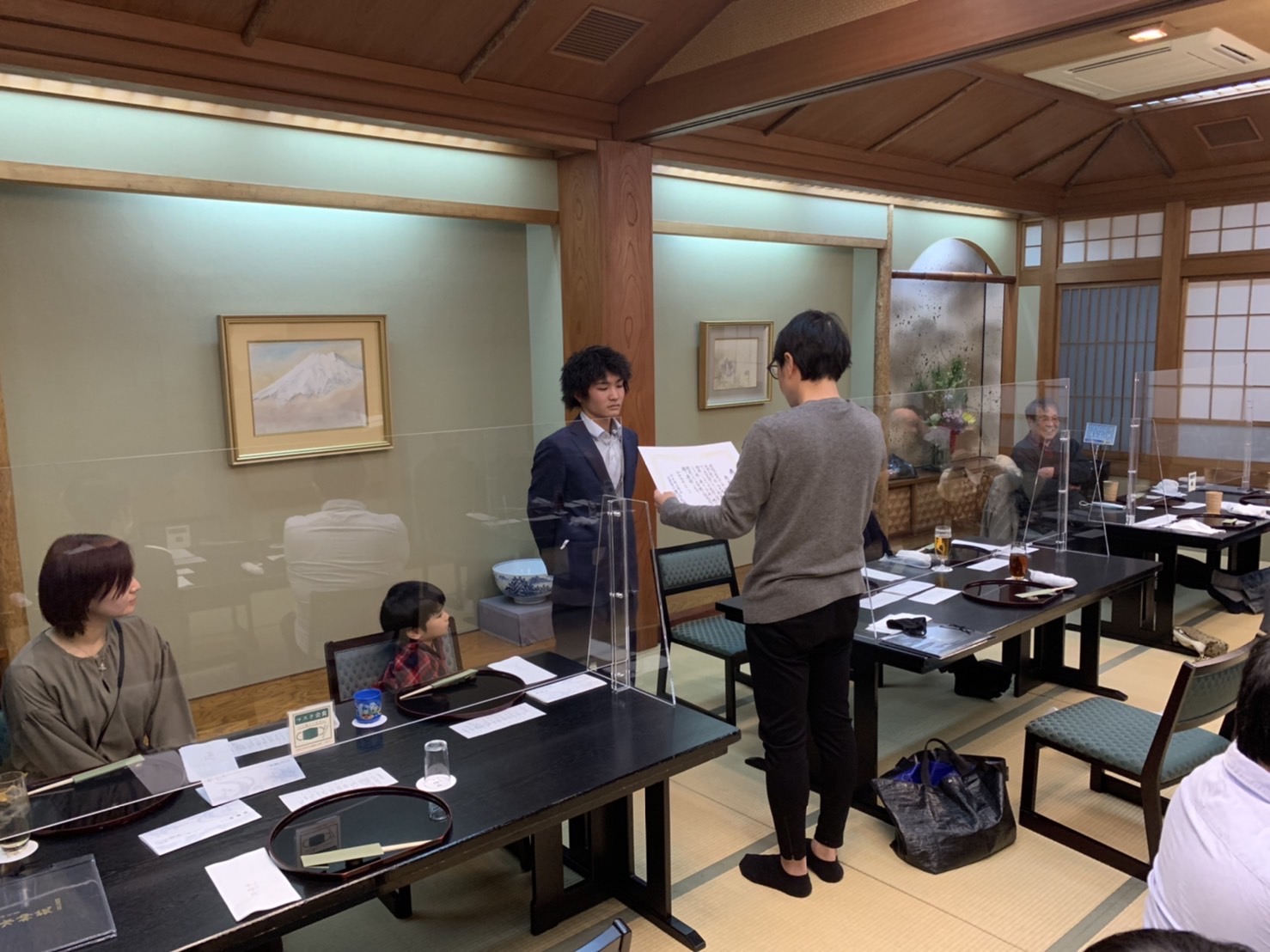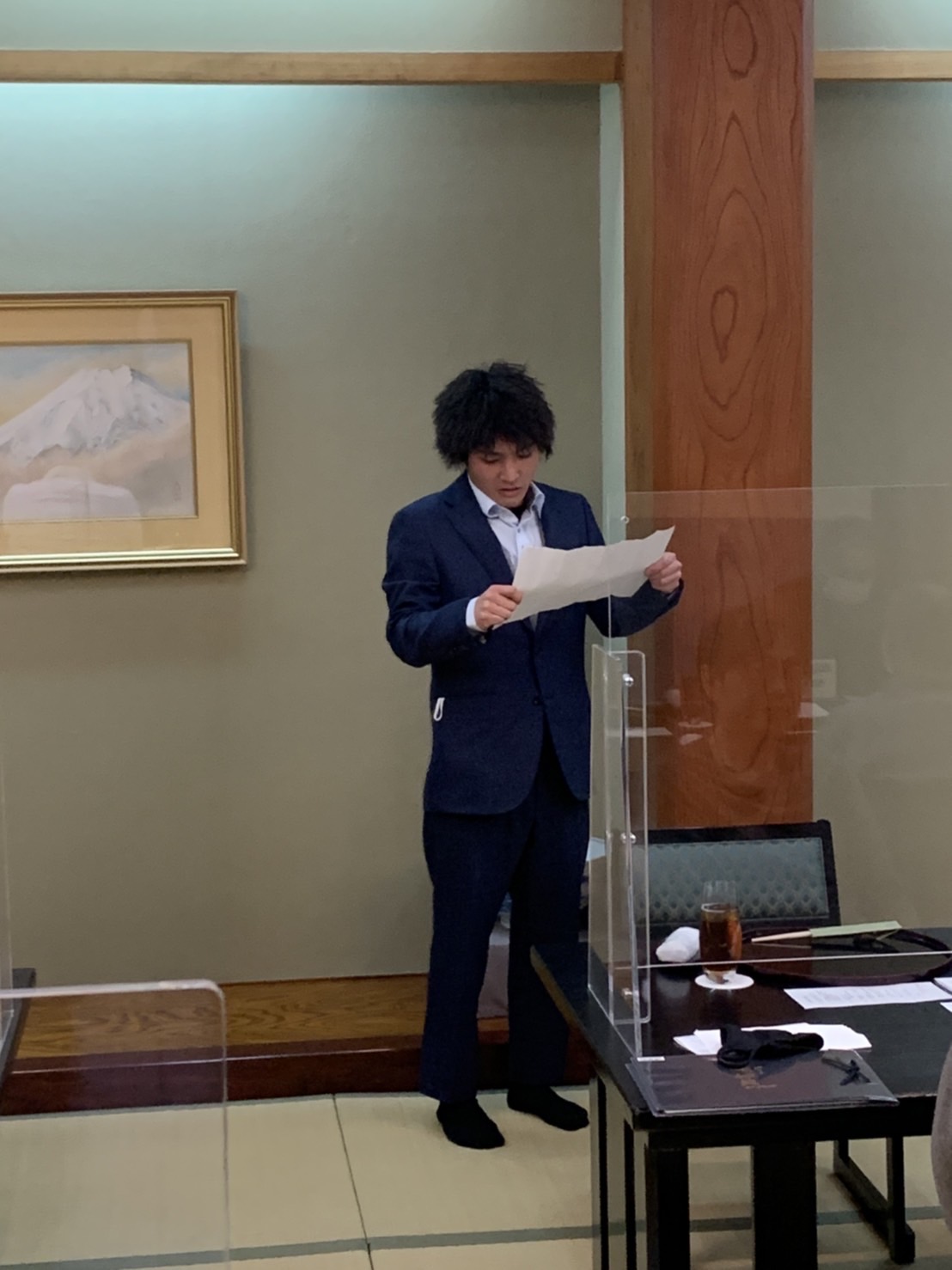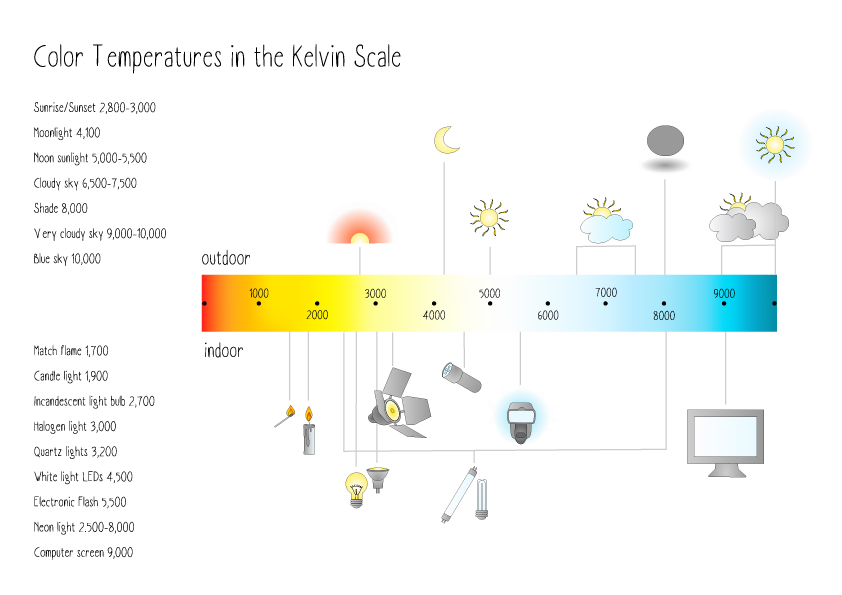家を建てたり、引っ越したりして心機一転。
センスのいい家、部屋にしたい!
でも、どうしたらいいかわからない。
センスのいい人はどうやってあんなお家にしているのか、誰か教えて!!!
って思いますよね。
素敵だなぁと思う家には、大抵センスのいい家具が置いてあります。
でも、それはどこかの小さなお店から見つけてきて1点ものを置いているわけでもなく、
(所さんのようにそういう方もいらっしゃいますが、、、)
定番の廃らない美しい家具たちを置いたり、飾ったり。
それに合わせて、自分の好きと思えて可愛いものを置いているのだと思います。
丸晴工務店のモデルハウスにもたくさんの素敵な家具がありますのでご紹介させていただきます。
今回は、その中のlouis poulsenの ”PHランプ”をご紹介させて頂きます。
モデルハウスにある家具雑貨
ペンダントライトPH4/3 《louis poulsen (ルイス・ポールセン)https://www.louispoulsen.com/ja-jp/privatek》

カイクリスチャンセンNO.42《宮崎椅子製作所 https://www.comfort-mart.com/?mode=f58》

ミナペルホネン《minä perhonen (ミナペルホネン)https://www.mina-perhonen.jp》


Yチェア《Carl Hansen & Son(カール・ハンセン&サン)https://www.carlhansen.com/ja-jp》

Louis poulsen ”PHランプ”について
「人に優しい光」言葉にするのは簡単でも、その実現は難しいものでした。
今から90年以上前、このテーマに率先して取り組んだデザイナーがデンマークのポール・ヘニングセンでした。
ポール・ヘニングセンは、デンマークの女優アグネスヘニングセンを母としてコペンハーゲンに生まれました。
1911年から1914年にフレデリクスベアのテクニカル・スクールで、また1914年から1917年にコペンハーゲンのテクニカル・カレッジで学び、伝統的な機能主義建築をスタートした後、彼の興味は照明の分野に移っていきました。
また、活動領域は文筆活動にも広がりジャーナリスト作家としても活躍しています。
第二次世界大戦初期、コペンハーゲンのティヴォリ公園の主任アーキテクトも勤めましたが、ドイツ軍占領時には他の多くの芸術家たちと同様、スウェーデンに亡命し、亡命先のスウェーデンではすぐさまデンマーク人アーティスト・コミュニティーの中心的人物となりました。
1920年から建築家として活動したヘニングセンは、常に照明を使う人の感覚を大切にしました。
1925年のパリ万国博覧会で、6枚の円盤形のシェードが光源を覆うことでまぶしい光源を巧みに隠しながら、周囲に温かい光を投げかける『パリ・ランプ』を発表しました。
電球のフィラメントが直接見えず、シェードの隙間から光がさす構造は、後の『PHランプ』と共通していました。
製作を担当した照明ブランドのルイス・ポールセンとともにヘニングセンは、より完成度の高い構造に早々に取り組み、翌26年に『PHランプ』の最初のモデルが生まれました。
この時初めてシェードの曲面に対数螺旋曲線が用いられました。
対数螺旋曲線とは、巻貝など自然の形態にもみられる渦巻きの形で、渦の中心に光源をおくとその光は同じ角度で曲線にあたり、広がっていく性質があります。
初期の『PHランプ』は塗装した銅板や乳白色のガラスを素材とする3枚のシェードを使用していました。やがて30年代までにシェードの枚数やサイズの異なるバリエーションが生まれ、モダンデザインの傑作として各国で人気を呼んでいます。
数々の作品
PH5
PH Artichoke Glass

Patera Oval


PH 3½-2½ Floor
最後に
センスのいい家にするために、このようなすばらしい照明や家具を取り入れてみてはいかがでしょうか?
格段に家の空間がより良いものに変わっていくと思います。
そんなお手伝いも、丸晴工務店では行なっております。
ご紹介可能な家具照明はこちら
https://www.marusei-j.co.jp/謹賀新年%E3%80%80本年もよろしくお願いいたします%E3%80%82/
ダイニングテーブルの照明位置についての記事はこちら。