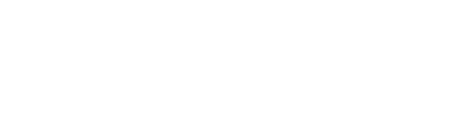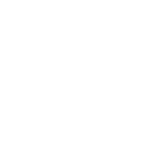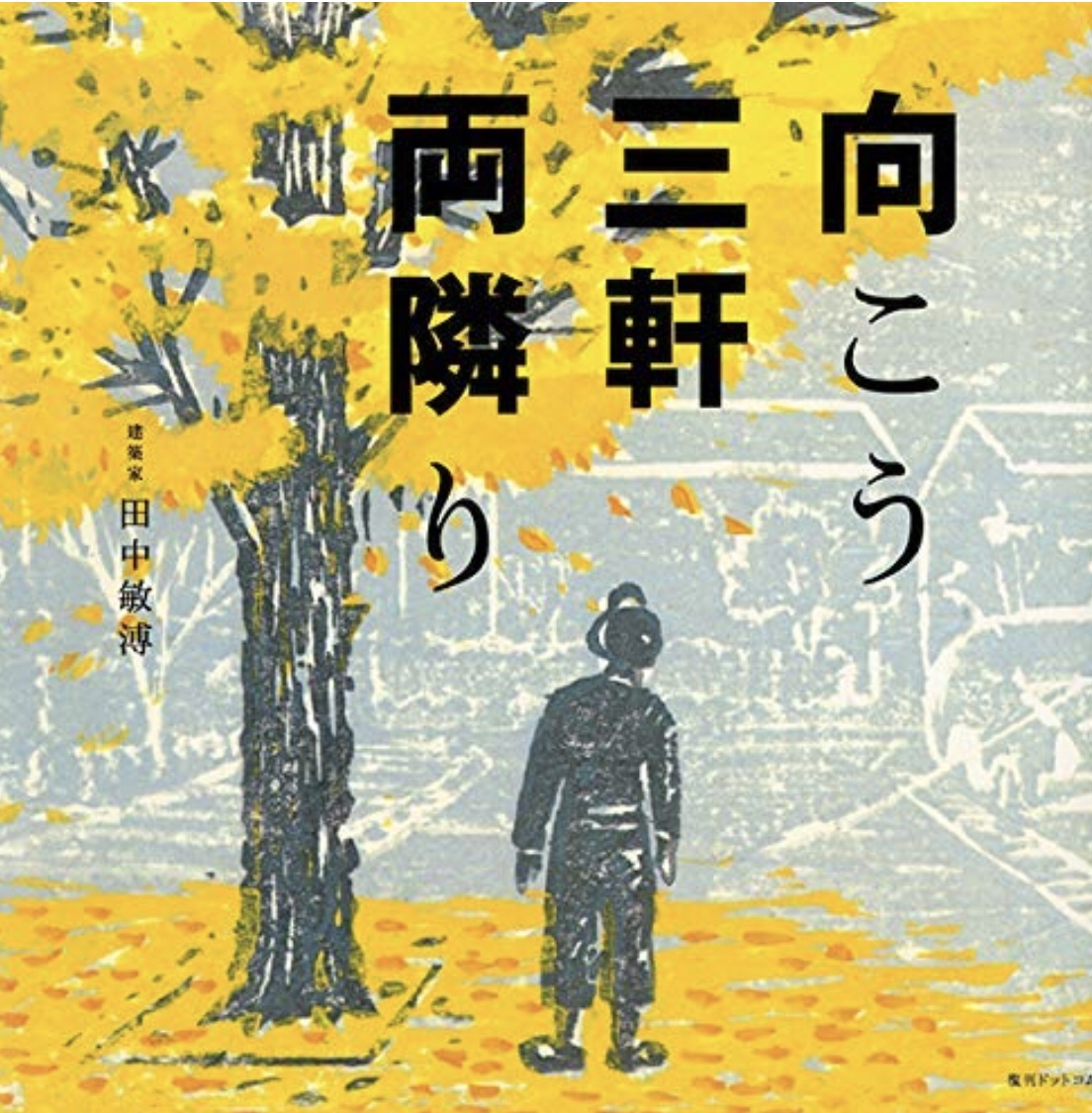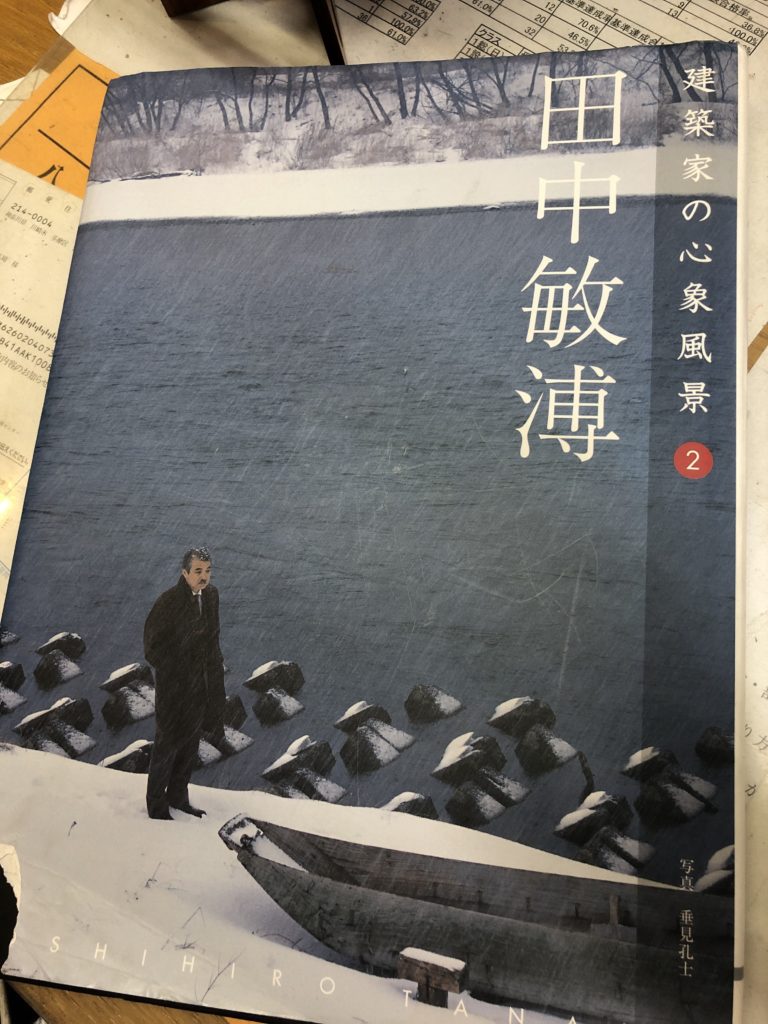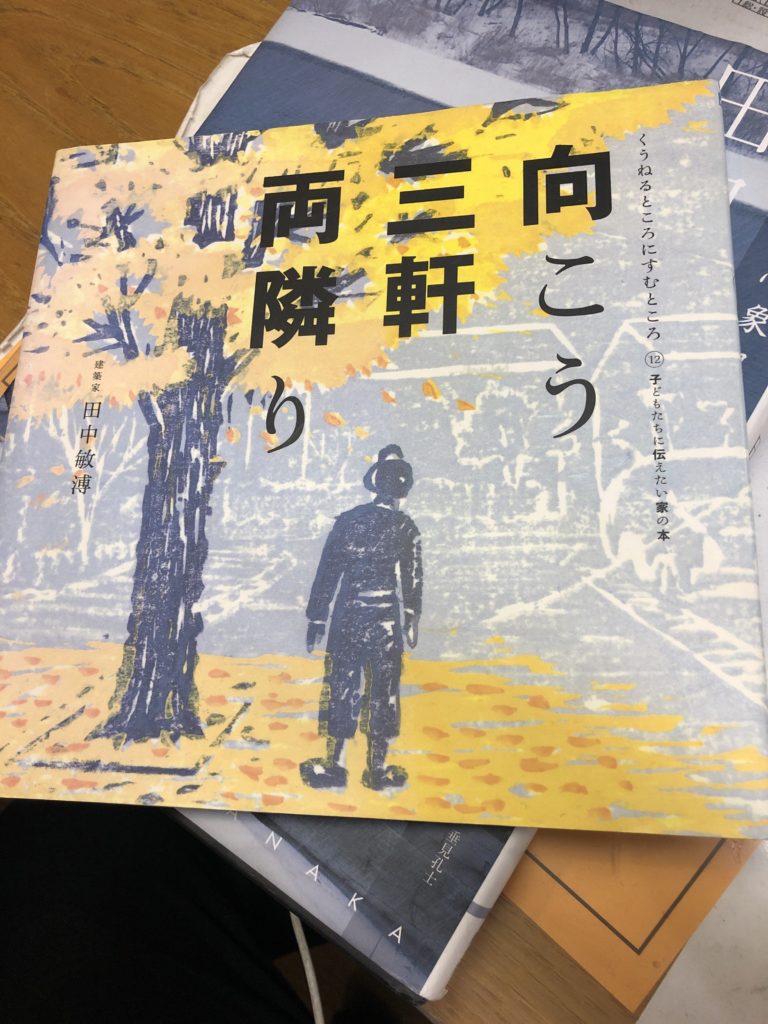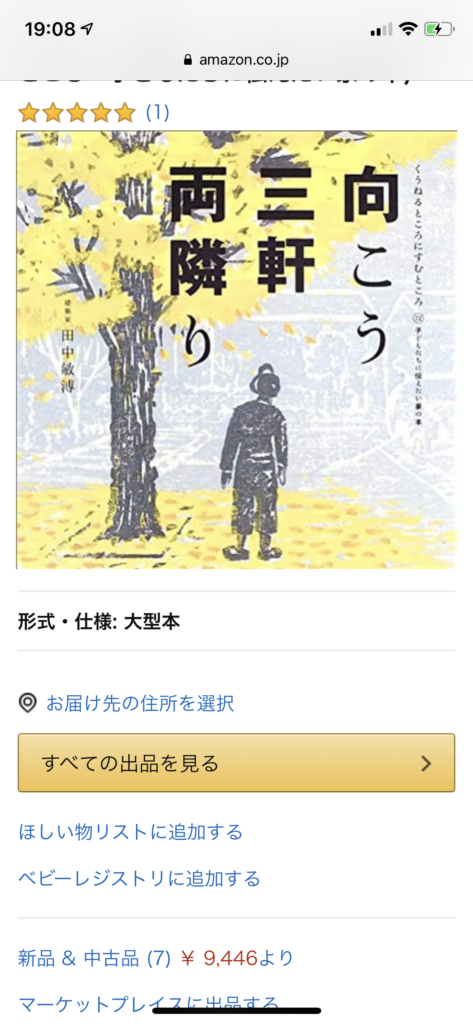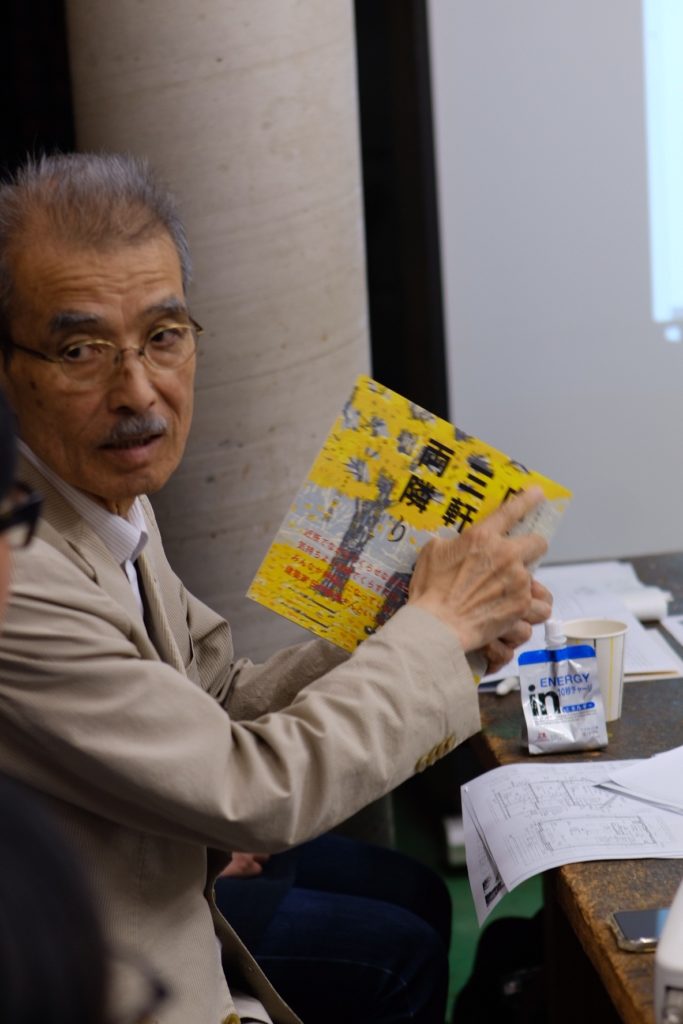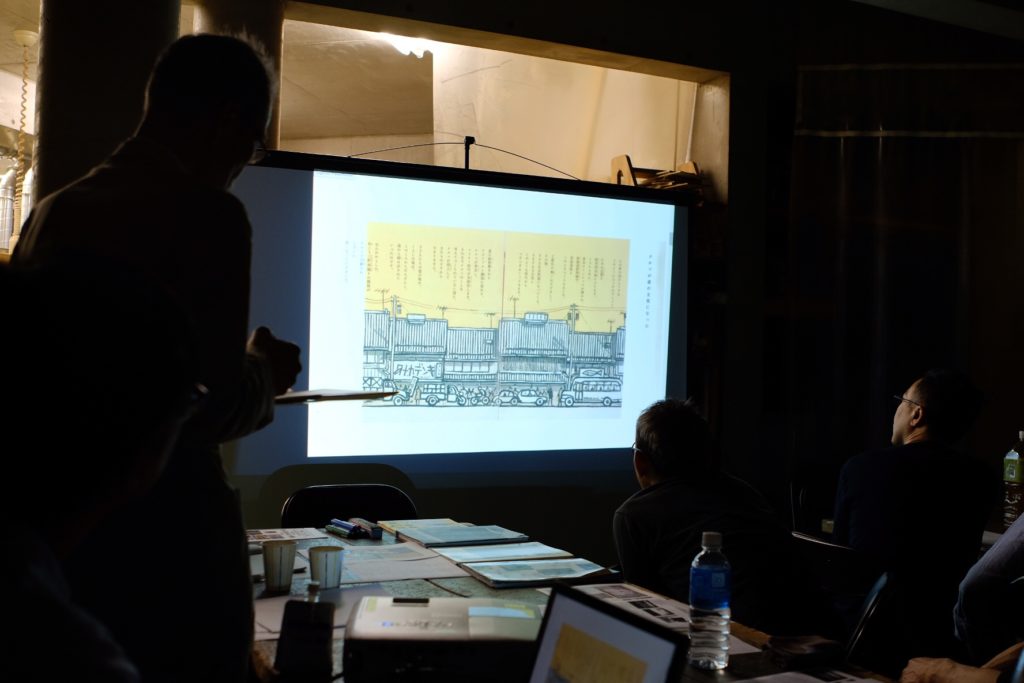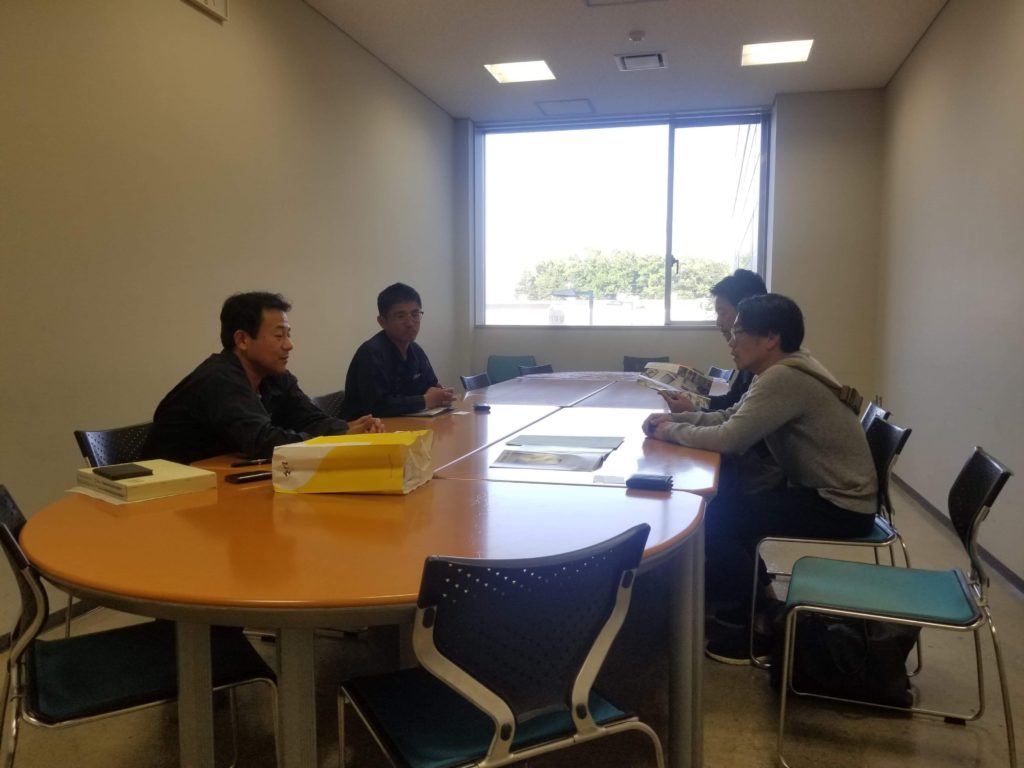みなさん、こんにちは。神奈川県川崎市を拠点に木の家づくりを手がける丸晴工務店です。
弊社は大工の先代が起こし、木と大工技術にこだわる工務店。今回は、木のクオリティの要となる「乾燥方法」についてお話したいと思います。
木を乾燥させる理由とは?
木の性質は、育った環境に負うところも大きいのはもちろんですが、木を住宅に使うためには、「乾燥」という工程が必要になります。
というのも、山で伐採した木は多くの水分を豊富に含んでおり、そのままでは使うことができません。
木は山で生えている状態だと、多くの水分を含んでいます。水分を含む指標を「含水率」と呼びますが、適切な含水率になるまで水分を落とさないと、十分な強度が担えなかったり、家を建ててから乾燥による収縮・反りなどの変形が起こってしまいます。
家の構造を支える梁・柱にこのような変形が起こると、家自体に歪みが生じたり強度的な問題が出てきてしまうのです。
たとえば杉ですと、伐採前の生木の状態では自重の約1.5〜2倍、含水率が150〜200%ほどの状態から、梁や柱の構造材にするには20〜25%ほどまで含水率を落とす必要があります。
「人工乾燥」「天然乾燥」その違いは?
その「乾燥」にも手法があり、「人工乾燥」と「天然乾燥」に大別することができます。
「人工乾燥」は、木材を機械に入れ、蒸気や高周波をあてて人工的的に水分を落とす方法です。
一方「天然乾燥」は梁・柱や板などに製材した状態で木を積み上げて太陽と風の力で水分を落としたり、伐倒した状態で樹皮や枝葉がついた状態のまま、葉の蒸散作用を利用してじっくりと水分を落としていきます。
自然のサイクルにのっとって水分を落とすので、化石燃料に頼ることもなく、地球にやさしいエコロジカルな乾燥方法です。

現在流通している材は、圧倒的に「人工乾燥」。
というのも、「天然乾燥」は水分を落とすのに時間がかかるのです。
「人工乾燥」と一口にいっても高温・中温・低音などさまざまな温度帯による乾燥方式がありますが、乾燥に要するのはおおよそ1〜2週間ほど。対して「天然乾燥」は半年〜2年もの時間がかかります。
ただ「人工乾燥」で主流の高温乾燥は、乾燥期間が大幅に短縮できるというメリットはあるものの、100℃を超える乾燥庫のなかで木の水分を細胞から抜く際に、油分も抜けて、色・ツヤなど木が本来もつ良さまで損われてしまうのです。
また見た目には問題がなさそうでも、内部で繊維が断ち切らたような割れを起こしていることもあり、桧はさほど問題ないのですが、材種によっては耐久性や構造的な強度上のデメリットを指摘する声もあります。
天然乾燥材

高温乾燥材

木、本来の力を引き出す天然乾燥
丸晴工務店が使っている木材は、吉野や天竜地方の昔ながらの天然乾燥材。
木の香りもかぐわしく、美しい色・ツヤは経年変化により味わいを増し、住まい手の皆さんと一緒に育っていきます。
柱や桁がでるような意匠ですとやはり人工乾燥は使いたくないですね。
また油分は、色・ツヤだけでなく、ノミの切れもよく加工ができるというメリットももたらします。
さらには木の細胞が梅雨時のような湿気の多い時期は水分を吸ったり、冬場など乾燥した季節には水分を放出してくれるので、調湿性能にも長けています。
調湿性は、細胞が収縮・膨張する証です。ただこのような細胞の動きの影響で、天然乾燥の柱はその表面に、割れが生じてしまいます。
しかしこれは、柱として欠陥品というわけではありません。強度的に問題が生じるわけでもなく、木の性質を活かしているからこそ起こる、自然な営みの一つなのです。